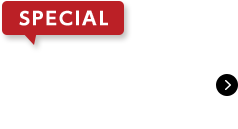ボトックスを打ちたいと考えつつ、内出血に不安を抱く人は少なくありません。ボトックスは注射で行う施術であり、注射には少なからず内出血を伴います。しかし顔に内出血が出るのは嫌だ、と考えるのは無理もないことでしょう。
本記事では、ボトックスにおける内出血について、原因や治るまでの期間、予防策などを解説します。参考にして、
内出血は必要以上に恐れるものではないことを知ってください。
ボトックスとは?

ボトックスは正確には製品名であり、正式名称はボツリヌストキシンです。つまり、ボトックスもボツリヌストキシンも施術内容に違いはありません。
効能は、
注射した部位の筋肉の収縮を弱めることです。この効能を利用してさまざまな審美治療に使用されます。また、美容施術だけでなく医療の世界でも治療としてボトックスは用いられています。
ボトックスのメリット
ボトックスはさまざまな施術に使用され、打つ部位によって審美性の効果が異なります。
たとえば、上唇の上に打つと人中短縮の効果を発揮します。これは上唇を下に引っ張る筋肉を弱めることで、唇が上向きになるためです。また、エラの部分に打つことでエラ張りを軽減できます。
エラ張りの原因が筋肉である場合、噛む筋肉を弱めて小さくさせることで、エラ張りが解消されるためです。
他にもさまざまな部位に注入でき、それぞれで嬉しいメリットがあります。
ダウンタイムに起きる症状
ボトックスのダウンタイムに起きる症状は、主に内出血です。
注射針の傷とそれに伴う赤みもありますが、傷と赤みは内出血と比べてすぐに消失するため、気になることはないでしょう。
メイクで隠すこともできますが、顔に内出血が出るのはやはり気になってしまうという人は少なくありません。
内出血とは?
内出血とは、皮膚の内側で血管が損傷し、血液が漏れ出た状態のことです。
皮膚が傷ついているわけではないため、外には出血しません。しかし中で出血したのが皮膚越しに透けて見えるため、審美性は低下してしまいます。
内出血はなぜ起こる?
内出血は、皮膚の内側で血管が傷つくことにより発生します。注射で内出血が起こるのは、注射針が毛細血管などに傷をつけてしまうためです。
そのため採血や点滴など、
どんな形であれ針を使用する際には内出血のリスクは生じます。まれに「ボトックスを打つと内出血が生じる」と考える人もいますが、ボトックスそのものが内出血を引き起こしているわけではありません。内出血の原因は、あくまで注射の針です。
内出血による肌色の変化
内出血は傷の治り具合によって見た目の色が変化します。そのため、
自分があとどれくらいで治るのか、見た目からある程度推測することができます。
色の変化と段階は以下のとおりです。
【内出血の色と傷の関係】
| 色 |
傷の段階 |
| 赤 |
内出血した直後 |
| 紫・青 |
出血した血が溜まっている |
| 緑・茶色 |
出血が吸収され始めている |
| 黄 |
治りかけ |
人によって治るスピードはさまざまですが、
気になるからと不用意に刺激を与えると、治りが遅くなることがあります。なるべく手で触れたりしないよう気をつけましょう。
内出血が治るまでの期間
注射によって生じた内出血が治るまでの期間は、
一般的に長くとも2週間ほどです。ただしこの期間は目安であり、人によって多少前後することもあり得ます。いずれにしろ、必ず治るため心配しすぎることはありません。
もしも内出血が数ヶ月、あるいは年単位で治らないという場合は、何か別の疾患の表れという可能性があります。その場合は審美性に関係なく、一度医療機関を受診した方が良いでしょう。
内出血は必ず起こるのか?
内出血は、ボトックスを受けた人すべてに必ず起こるというわけではありません。
同じ人が同じクリニックで施術を受けても、起こるときと起こらないときがあります。
施術を受ける人のその日の肌のコンディションによって起こりやすい・起こりにくいという差はあります。しかしいずれにしろ、完全に予防することは不可能であることは覚えておきましょう。
内出血は施術ミスではない
ボトックス注射による内出血は、施術ミスではありません。
まれにではありますが、内出血が酷い場合「これは施術ミスなのでは?」と疑ってしまう人がいます。しかし内出血は、
どんなに腕の良い医師であっても100%避けられるわけではありません。
施術のミスとは、取り返しのつかない影響を与えてしまったり、不要な怪我などを引き起こしてしまったりという場合を指す言葉です。
内出血は治るものであり、針を使用する施術の上で避けて通れないものでもあります。
内出血を減らすために

内出血は100%防ぐことはできないと前述しましたが、
リスクを減らすことは可能です。
内出血が気になるという人は、できるだけ内出血が出ないように、出たとしても軽度のもので終わるように、自分でできることはしっかりと行いましょう。
止血をしっかりと
施術が終わったら、まずは止血をしっかりと行いましょう。
止血方法は通常の注射と同じで、針を刺した部分をぐっと強く押す圧迫止血です。
止血をしなかったからといって、健康上の支障はありません。そのためしばしば止血をしない人が見受けられますが、内出血を避けたいのであればきちんと行うべきです。
体を温めすぎない
体が温まると血行が良くなり、血管が広がって出血しやすくなります。そのため、施術後に体を温めすぎると内出血が酷くなってしまうことがあります。
だからといって体を冷やすのも健康に良くありません。
過ごしやすい温度で過ごし、激しい運動やサウナなど体温が極端に上昇するような行動は、施術後数日は避けましょう。
腕の確かな医師から施術を受ける
腕の良い医師は、いたずらに血管を傷つけることが少ないため、内出血が起こるリスクを減らすことができます。内出血を防ぎたい場合は、実績のあるクリニックを選びましょう。
ただし、これも完全ではありません。
どうしても血管に触れてしまう場合もありますし、体質によっては内出血が生じやすい場合もあります。あくまでリスク低減であり、リスク0にはならないことを覚えておきましょう。
まとめ
顔の施術において内出血は気になるポイントです。しかし一方で、避けられない場合もあるのが現実です。
できる限りリスクを減らし、内出血が起こりにくいよう、また、酷くならないよう知識をつけましょう。
また、内出血が起こったからといって焦る必要はありません。時間の経過とともに綺麗に治るため、見た目の目立ち具合に不安がらず、ゆったりした気持ちで治るのを待ちましょう。
 ボトックスは正確には製品名であり、正式名称はボツリヌストキシンです。つまり、ボトックスもボツリヌストキシンも施術内容に違いはありません。
効能は、注射した部位の筋肉の収縮を弱めることです。この効能を利用してさまざまな審美治療に使用されます。また、美容施術だけでなく医療の世界でも治療としてボトックスは用いられています。
ボトックスは正確には製品名であり、正式名称はボツリヌストキシンです。つまり、ボトックスもボツリヌストキシンも施術内容に違いはありません。
効能は、注射した部位の筋肉の収縮を弱めることです。この効能を利用してさまざまな審美治療に使用されます。また、美容施術だけでなく医療の世界でも治療としてボトックスは用いられています。
 内出血は100%防ぐことはできないと前述しましたが、リスクを減らすことは可能です。
内出血が気になるという人は、できるだけ内出血が出ないように、出たとしても軽度のもので終わるように、自分でできることはしっかりと行いましょう。
内出血は100%防ぐことはできないと前述しましたが、リスクを減らすことは可能です。
内出血が気になるという人は、できるだけ内出血が出ないように、出たとしても軽度のもので終わるように、自分でできることはしっかりと行いましょう。
 ボトックスは正確には製品名であり、正式名称はボツリヌストキシンです。つまり、ボトックスもボツリヌストキシンも施術内容に違いはありません。
効能は、注射した部位の筋肉の収縮を弱めることです。この効能を利用してさまざまな審美治療に使用されます。また、美容施術だけでなく医療の世界でも治療としてボトックスは用いられています。
ボトックスは正確には製品名であり、正式名称はボツリヌストキシンです。つまり、ボトックスもボツリヌストキシンも施術内容に違いはありません。
効能は、注射した部位の筋肉の収縮を弱めることです。この効能を利用してさまざまな審美治療に使用されます。また、美容施術だけでなく医療の世界でも治療としてボトックスは用いられています。
 内出血は100%防ぐことはできないと前述しましたが、リスクを減らすことは可能です。
内出血が気になるという人は、できるだけ内出血が出ないように、出たとしても軽度のもので終わるように、自分でできることはしっかりと行いましょう。
内出血は100%防ぐことはできないと前述しましたが、リスクを減らすことは可能です。
内出血が気になるという人は、できるだけ内出血が出ないように、出たとしても軽度のもので終わるように、自分でできることはしっかりと行いましょう。